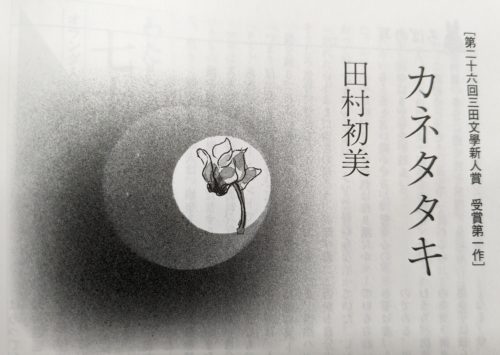
 ・『カネタタキ』(田村初美/三田文學冬季号2023)
・『カネタタキ』(田村初美/三田文學冬季号2023)
被差別部落に生まれ、生きるとはどういうことか。島崎藤村の『破戒』や中上健次の『枯木灘』にもなかった「生活」そのものから<幻想>を取り払って見る視点がここにはあります。当たり前のことですが、被差別部落も「日本」という国家にある限り、同じ制度の中で日々の日常をつつがなく営まんがため、教育や就労、結婚、出産、老いや入院、介護といった様々な状況に様々な事象を刻みながら、そこでの暮らしが営まれています。
「自由」や「平等」を声高に主張し、差別の不当性や不条理を提示するより先に、<生活>が同じように営まれているということ、あるいはそのことを求めているということ、その土台を共有し合うことが、差別、被差別両辺の者たちにとっての出発点でしょう。
本作はまずそこへ立ち返らせてくれます。
幻想を剥いでごらんなさい。まずはあなたの意識と、その志向性を疑いなさいと。
わたしたちは、差別的事象を目にしたりかかわったとき「偏見で見ないようにしましょう」と言いつつ、実は自らがその「偏見の呪縛」にがんじがらめとなり、被差別者たちのごく当たり前の「生活」の現場を見ようとしてしないことが多いです。それはおそらく部落民の人たちも陥っている陥穽と言えます。
では、もしも「生活」の地点から差別の社会的構造を知った場合どうなるか。象徴的な場面を作者は提示します。それは、幼児から理不尽ないじめをうけてきた中学三年の厚子が、身内から自分の住む村が被差別部落であったことを聞き知ったときの反応です。
厚子はそれまでの自分の体験と認識の線がつながっていくことで、まさに直感的にその虚構を見抜きます。そしてそれは15歳であるゆえの、ある意味で<純粋な生活者>としてのしたたかさとしなやかな感性で言葉を発するのです。
「被差別部落であることが原因でよかった。そんなアホなことが原因で本当によかった」そして、これまでいじめを繰り返してきた周囲の子たちを「皆、可愛らしいがゆえに可哀そうだと思った。厚子は同級生たちを決して好いてはいないけれど、誰も恨んでいない自分に、このとき気づ」きます。
ここには、人知を超えた<神話性>やひとかたならぬ大きな<ドラマ>の中に生きている人々も登場することはなく、日常ゆえに厳しくも尊く、そして儚い現実が丁寧に描かれています。まるでそれは本題の「カネタタキ」の小さな虫の闇に発する、微かであっても、一個の鼓動を持った生命を宿す音を、けっして聞き漏らすまいとする作者の姿勢を示すかのようです。その徹底した描写は、「差別」を扱った作品に、最終的にどこかで「解釈」や「表現」としての解消のカタルシスを求めるのは、それこそがいわれなき「偏見」であり「差別」に通じるのではないか、と問うているかのようでもあります。
今、『部落差別』をテーマとした小説は田村初美の出現によって確かに新しいステージへ来た、そんな予感と実感を持たさせてくれる作品だと思います。

『カネタタキ』(田村初美/三田文學冬季号2023)を読んでみて。
コメントはまだありません















